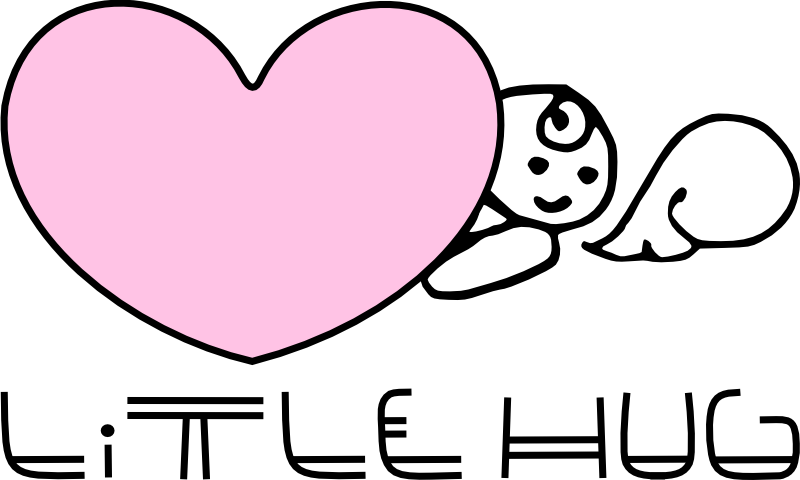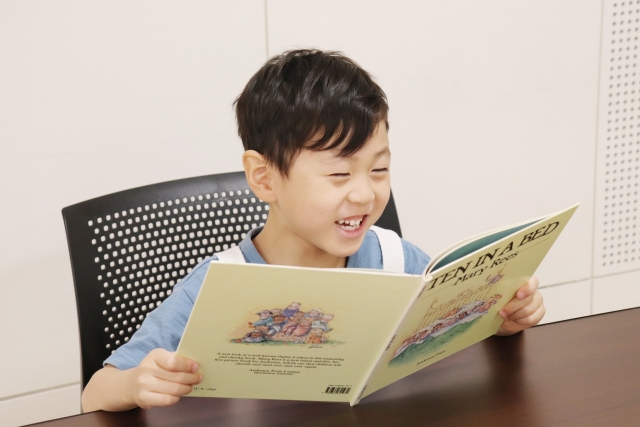「うちの子は英語を聞き取れてないみたい…」
「英語が聞き取れるようになるために、家庭でできることはある?」
このように感じたことはありませんか?
単語は知っている、文法も勉強した、なのに聞き取れない…それは、子どもの「耳」が、英語に使われる周波数に慣れていないからかもしれません。日本語に慣れた耳は、英語特有の高い音域をうまくキャッチできない場合があるからです。
本記事では、英語と日本語の音声的な違いを解説しながら、家庭でできる具体的なリスニング改善法をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
周波数とは?

周波数とは、音の振動の速さを示す指標で、単位はヘルツ(Hz)で表されます。音の高さ(ピッチ)は、主にこの周波数できまり、人間が話す言葉もこの周波数の組み合わせによって構成されているのです。
また、音声学では、母音の特徴を決める周波数帯域を「フォルマント」と呼びます。とくにF1(第1フォルマント)とF2(第2フォルマント)が、母音の聞こえ方を左右する大切な要素。「あ」と「い」の違いも、このフォルマント周波数の違いによって生じています。
一方、子音には高周波成分が多く含まれ、とくに「s」や「sh」のような摩擦音は、日本語ではあまり使用されない高い周波数帯域が使用されます。この高周波成分が、日本語を母語とする人にとって、英語を聞き取りにくくする大きな要因の一つなのです。
音声は単純な一つの周波数ではなく、複数の周波数が重なり合った複雑な波形。この構造を理解すると、英語と日本語の音声的な違いが見えてくるでしょう。
日本語と英語の音声周波数の違い

言語によって使用する周波数帯域には違いがあります。
日本語の音声周波数は、主に125Hzから1500Hz程度の範囲に集中しています。なぜなら、日本語は母音が中心の言語であり、比較的低い周波数帯域で会話が成立するからです。
対して英語は、2000Hzから8000Hz、あるいは10000Hzまでの高周波帯域を幅広く使用。特に、子音(摩擦音など)において高周波数成分が多く含まれるため、日本語とは大きく異なる音響特性を持っています。
| 言語 | 主な周波数帯域 | 特徴 |
| 日本語 | 125Hz〜1500Hz | 母音中心、低周波帯域が主 |
| 英語 | 2000Hz〜12000Hz | 子音が多く、高周波帯域を含む |
| フランス語 | 1000Hz〜2000Hz | 中間的な周波数帯域 |
この周波数帯域の利用幅の違いが、日本人が英語を聞き取りにくい理由の一つとされています。しかし、周波数だけが全てではありません。音素やプロソディ(音の韻律)など、言語には様々な音声的特徴があり、これらが複合的に作用して聞き取りの難しさを生み出しています。
次の章では、周波数以外の音声的な違いについて詳しく見ていきましょう。
英語と日本語の「音の違い」は周波数だけではない
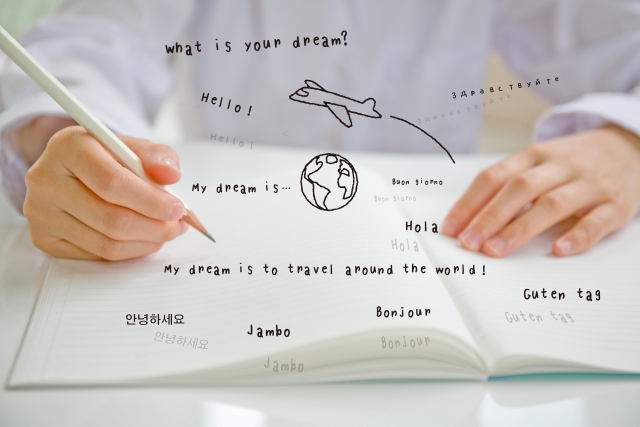
英語が聞き取りづらい理由は、周波数の違いだけではありません。音素の種類、発声方法、リズムやアクセントなど、多角的な違いが存在します。
日本語に存在しない音がある
英語には、下記のような日本語に存在しない音素が数多くあります。
【日本語に存在しない音素の例】
・「r」
・「th」
・「v」
・「sh」
これらのような子音は、日本語を話す人にとって習得が難しい音として知られています。
θ(think)やð(this)のような歯音、rとlの区別、vとbの違いなど、日本語には存在しない微妙な音の差異が、英語では意味の違いを生み出すのです。「light」と「right」、「vest」と「best」は、日本語話者には同じように聞こえても、英語では全く異なる単語になります。
さらに英語には、日本語に存在しない複雑な調音を持つ子音(/z/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/など)も多く、母音の数も日本語の5つに対して15以上存在します。この音素の多様性が、英語の聞き取りを複雑にしているのです。
リズム・アクセントの違いがある
言語のリズムやアクセントのパターンも、日本語と英語では大きく異なります。
日本語は、各拍がほぼ等間隔で発音する言語です。「さ・く・ら」の3つの音はそれぞれ同じ長さで発音され、高低のピッチ(ピッチレベル)で意味の違いを表現します。たとえば「橋(はし)」と「箸(はし)」は、高低アクセントによって区別されているのです。
一方、英語は強く発音される音節(ストレス)を基準に、弱い音節が短縮されたり曖昧に発音される言語です。
| 英単語 | 品詞 | 意味 |
| PROject | 名詞 | 計画 |
| proJECT | 動詞 | 投影する |
表のように、強勢の位置が意味を変えることもあります。
イントネーション(抑揚)のパターンも異なり、英語では文末の上昇・下降が疑問文と平叙文を区別し、感情表現も豊かです。日本語のような平坦なリズムではなく、波のような抑揚が英語の特徴と言えるでしょう。
この音韻的な違いを理解すると、リスニングの学習が進みやすくなります。
英語耳の育て方とは?幼少期からの音環境が大切

英語を自然に聞き取れる「英語耳」を育てるには、幼少期からの環境づくりが効果的です。聴覚の発達過程を理解することで、適切なアプローチが見えてくるでしょう。
赤ちゃんの聴覚の発達について
赤ちゃんの聴覚は驚くほど優れています。生まれたばかりの新生児でも、広範囲の周波数を聞き取る能力を持っているのです。
さらに、生後6か月頃までの日本人の赤ちゃんでも、英語の「r」と「l」の違いや、フランス語の鼻母音を聞き分けられると言われています。しかし、成長とともに母語の音声体系に最適化されていくため、母語にない音素の識別が難しくなっていくのです。
大人になると聞こえなくなる音域
成長とともに聴覚の感度は変化します。特に高周波数帯域の聴力は年齢とともに低下する傾向があり、英語の子音に含まれる高周波成分が聞き取りにくくなるのは、この生理的な変化も関係しています。
だからこそ、幼少期から英語の音に触れる機会を増やすと良いでしょう。子どもの柔軟な聴覚は、新しい音声パターンを吸収しやすいです。早期から多様な環境を提供することで、英語の周波数帯域にも、自然に対応できる耳が育っていくでしょう。
そこで、日常の中で英語の音に触れられる「リトルハグ」の英語ベビーシッターを利用してみてはいかがでしょうか。「リトルハグ」のベビーシッターサービスでは、外国人ベビーシッターが、遊びや会話に英語を自然に織り交ぜます。おもちゃや絵本で遊ぶ時間や、おやつを食べるひとときにも英語が飛び交い、子どもは無理なく、楽しみながら英語特有の音に慣れていけるでしょう。
英語を聞き取るリスニング力を高める方法

ここからは、実際にリスニング力を高めるための具体的な方法をご紹介します。日常生活に取り入れやすい工夫や、効果的なトレーニングを見ていきましょう。
英語のリスニングにおすすめの教材やツール
幼児向けには、英語の歌や韻を踏んだナーサリーライム(童謡)が効果的です。「Mary Had A Little Lamb」や「Old MacDonald Had a Farm」など、リズムとメロディーに乗せて英語の音に触れられます。繰り返しのパターンが多いため、子どもが自然に覚えやすい教材です。
アニメーション動画も優れた教材になります。「Peppa Pig」や「Bluey」といった作品は、日常会話のスピードで自然な英語が使われており、視覚情報と組み合わせて理解しやすい構成と言えるでしょう。
小学生以上には、英語のYouTube動画やオーディオブックも良いでしょう。興味のあるテーマを選ぶことで、継続しやすくなります。
「リトルハグ」では、子どもの年齢や興味に合わせて、ベビーシッターが適切な英語の絵本や遊びを提案します。プロの視点で選ばれた教材で、効率的にリスニング力を育てていけるでしょう。
「子どもと一緒に読むおすすめの本が知りたい!」という方は、こちらの記事「英語絵本の読み聞かせは有効か?おすすめをご紹介」も合わせてご確認ください。
毎日の習慣に取り入れるコツ
英語のリスニング力向上には、継続的な音声インプットが欠かせません。日常生活の中に自然に組み込むことで、無理なく続けられます。
たとえば、通学時間や家事の合間など「耳が空いている時間」を活用しましょう。英語のポッドキャストやオーディオブックを流しておくだけでも、英語の音声パターンを学習できます。
最初は内容を完全に理解できなくても問題ありません。英語の音声に触れる時間を増やすこと自体が、耳を慣らすトレーニングになるのです。朝の支度中、移動中、寝る前の10分間など、少しずつでも毎日続けましょう。
音読やシャドーイングの実施
聞くだけでなく、自分で声に出すことでリスニング力はさらに向上するでしょう。
音読では、正しい発音やイントネーションを意識しながら繰り返すことで、英語の音声パターンが身体に染み込んでいきます。
シャドーイングは、音声を聞きながらそのすぐ後を追いかけて真似する手法。音声と同時に発声するのではなく、0.5秒ほど遅れて追いかけます。この練習により、英語特有のリズムやイントネーション、音の連結や脱落といった自然な会話の特徴を体得できるのです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、短い文章から始めて徐々に長くしていくと効果的。1日10分程度でも、継続することでリスニング力は向上するでしょう。
まとめ:英語と日本語の周波数の違いを理解してリスニング力をアップしよう!

「英語が聞き取れない」原因は、決して子どもの努力不足ではありません。音の周波数帯域や音素の違い、リズムやアクセントのパターンなど、言語そのものに物理的な差があるからです。
だからこそ子どもの耳が柔軟な時期に、自然な形で英語の音に触れる環境を整えてあげることが、何よりの近道になるでしょう。
「リトルハグ」のベビーシッターサービスなら、英語が堪能な外国人ベビーシッターが、遊びや日常会話を通して自然に英語に触れる環境を提供します。特別な「勉強」ではなく、遊びや会話の中で自然に耳が育っていくでしょう。
「うちの子に合うかな?」
「どんなベビーシッターがいるの?」
このような疑問や不安も、お気軽にお聞かせください。
【リトルハグのお問合せはコチラ!】